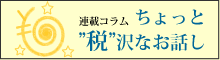その175(りらく2025年10月号)
立秋の過ぎた8月上旬。渓魚を求め、とある山奥の渓流に釣行しました。8月ともなりますと渓流釣りもいよいよ中盤です。この時期は、運が良ければ尺越えの大物に出会えるかもしれません。
国道から外れ、かなり荒れた林道を注意しながら奥へ奥へとひたすら車で進みます。やがて、峠を越えてしばらく下っていくと、ようやく目指す渓流が眼下に見えてきました。川面が陽の光でキラキラと輝いています。
目指す釣り場に着いて車を林道の脇に停め、早速準備に取りかかります。標高が高いので気温は20度前後でしょうか? 暑くもなく寒くもない丁度良い気温です。幸い、他に釣り人は見当たらず、渓流釣りの条件はそろっています。あとは自分の腕次第というところです。
支度もできて、いよいよ渓流に降り立ちます。見上げれば、真っ青な空に白い雲がたくさん浮かんで早(はや)秋の気配です。前の晩に用意した毛バリを釣り糸の先に結んで、竿を前後に振りながらラインを伸ばしていきます。毛バリ釣りのタックル(釣り道具)は、重さがたった数グラム程の毛バリを、重りは使わずに太めの釣り糸(フライライン)の質量を利用して釣竿(フライロッド)を前後に振りながら10メートル以上先のポイントまで飛ばすことができる仕掛けになっています。フライロッドの長さはわずか2メートル30センチ程しかないのですが、その5倍も遠くまで毛バリを飛ばすことができます。ヤマメやイワナは、とても神経質な魚で、人の気配を感じると川底深く潜ってしまったりエゴと呼ばれる岩の隙間に隠れてしまったりして出てこなくなるので、なるべく人の気配を感じさせないよう遠くから釣るのが鉄則です。
何投目かで反応があったのですが、なかなか毛バリを咥えるところまでいきません。どうも毛バリの種類がこの渓流には合っていないようです。毛バリを別の種類のものに取り換え先程と同じポイントに投入したところ、一投目で水面を割って渓魚が飛び出してきました。一呼吸置いて竿を立てフッキングを試みると、竿がしなり、手に「ズン!」という重い感触が伝わってきました。うまくフッキングしたようです。渓魚が必死の思いで右へ左へと走ります。岩陰や岩の隙間に逃げ込まれると面倒です。岸の方に後退しながら徐々に獲物を手前に引き寄せます。やっとの思いで取り込むと尺(約30センチ)には届きませんでしたが、体高のある良型のヤマメでした。しっかりと毛バリを咥えています。写真に収めて毛バリを外し、そっと流れに戻してやりました。遠く仙台から3時間かけて来た甲斐があったというものです。その後もヤマメの他、イワナも釣ることができ、大満足の釣行となりました。



話は変わって、高齢者の認知症対策としての財産管理についてご紹介しています。前回は、高齢者の「本人確認」の問題についてご紹介致しました。「本人確認」ができなくなりますと、ご自分だけでなくその配偶者や子どもであってもご本人の財産に関して一切何もできなくなる、という問題が生じます。
このような場合は、「成年後見制度」の内「法定後見制度」を利用して、ご本人の財産管理を行うことが可能です。この制度によりますと本人に代わって家庭裁判所が選任した「法定後見人」が、ご本人(「被後見人」といいます。)の財産管理を行うことになります。「法定後見人」は、被後見人が所有する不動産、預貯金その他の金融資産、年金等の財産管理の他、税金や公共料金の支払い、社会保障関係の手続き、被後見人が行うべき法律行為(遺産分割協議、売買契約、賃貸借契約等)を本人に代わって行います。
このように法定後見人は、被後見人に代わってかなり大きな権限を有するのですが、問題がないわけではありません。次回は、法定後見制度のメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。