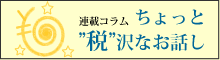その173(りらく2025年8月号)
梅雨入り前の6月上旬。山形県と秋田県の県境にそびえる鳥海山(標高2236m)に登ってまいりました。鳥海山の登山口はいくつかありますが、今回は日本海側の鉾立登山口(標高1160m)から入山し、途中「七五三掛」(しめかけ)という地点から千蛇谷という外輪山の内側の深い谷に降りてそこから頂上(新山といいます)を目指す計画です。
登山口から頂上までの標高差は1100m程、距離にして7・5㎞もあります。しかも、今回は頂上を踏むだけでなく、そこから雪渓で覆われた千蛇谷をスキーで滑り降りるのが目的でしたので、重たいスキーの板を背負っての登山となりました。
当日は、早朝の5時にスタートして頂上を目指しました。登山道沿いにはシラネアオイやハクサンイチゲなどの高山植物の花々が目を楽しませてくれます。さらに進んで標高1500m付近から登山道は雪渓に覆われ、一面真っ白な風景となりました。途中山頂との中間に位置する御浜小屋を過ぎると、鳥海山の頂が遠くに見えてきました。七五三掛から急な外輪山の崖を慎重に下り、何とか千蛇谷の深い谷底に降り立つことができ、目指す新山の頂もようやく間近に見えてきました。
千蛇谷は、冬の間に降り積もった雪が雪渓となっていて、新山の頂上付近まで続いています。この千蛇谷ですが、その昔、鳥海山の大噴火により溶岩流や火砕流が猛烈な勢いで流れ下り、それらは、はるか先の日本海まで達したとの記録があります。あたかもそれは一千匹もの蛇がこの谷を一気に駆け下りたかのような様相だったのでしょう。
そんなことを思い浮かべながら、深い谷を一歩一歩踏みしめるように登っていくと、ようやく頂上直下の大物忌神社(おおものいみじんじゃ)にたどり着きました。お社(ルビ=やしろ)に参拝した後、岩だらけの山頂に上がり、頂上からの360度の絶景を楽しみます。眼下には、いましがた登ってきた深い谷が奈落の底まで続いているかのように見え、足がすくむ思いです。
山頂での感動もそこそこに、今度はこの谷をスキーで滑り降りなければなりません。早速スキーを履いて山頂直下の急斜面を慎重に滑り、何とか無事下山することができました。往復10時間のビックマウンテンを十二分に堪能した山行となりました。




話は変わって。これまで、相続税対策としての生前贈与や住宅取得資金のための親子間での金銭消費貸借についてお話ししてまいりましたが、今回から高齢者の認知症対策としての財産管理の方法、特に家族信託についてご紹介してまいりたいと思います。
国(内閣府)の調査によりますと、60歳以上の世帯の貯蓄額は平均で2400万円前後となっています。全世帯の貯蓄額の中央値は1000万円程ですから、高齢者は、他のより若い世代と比べて2・4倍もの貯蓄額となっています。これは、退職等により収入が減少していく中で老後の生活資金を貯蓄でまかなおうとしていることの表れでもあります。
ところが、認知症や脳梗塞などの重い疾患によりご本人の判断能力が失われてしまいますと、せっかくの貯蓄も引き出して使うことができなくなるという問題が生じます。金融機関や証券会社ではさまざまな事情から「本人確認」ができなければ、たとえ配偶者や子どもであっても、本人の意思確認ができないという理由で、預金の出し入れや株式や債券の売買ができません。この問題について次回さらに詳しくお話ししてまいりたいと思います。