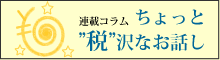その171(りらく2025年6月号)
里山の雪が解けた3月の下旬、自宅の薪ストーブ用の燃料となる薪を補充するため、許可を得て知り合いの方が所有する山林へ向かいました。毎年この時期は山に入り、林道に積んである原木を「玉切り」といってチェーンソーで長さ40センチほどの丸太にカットし(カットしたものを「玉木」といいます)、自宅に運び、割るのが年中行事のひとつとなっています。割ったあとは、自宅の周りに設置してある薪棚に2年間積んで十分乾燥させますと、よく燃えて火持ちの良い立派な薪になります。
薪の材料となる原木は、コナラ、カエデや山桜等の堅い広葉樹です。東北の里山には、今でもこのような雑木林の山がたくさんあります。昔は、どこの家にもかまどや囲炉裏があって、これらの広葉樹を切り出して、炭にしたり、そのまま薪にしたりしていたのです。私が幼少の頃も自宅の台所にはかまどがあり、母親が薪でご飯を炊いたり調理したりしていた記憶があります。
現在は電気やガスが一般の家庭に普及していますので、都会では薪を燃料にするところはほとんどなくなってしまいましたが、寒い時期の暖を取るために、今でも薪ストーブを導入しているところもあり、静かなブームとなっています。薪ストーブは、薪の準備等、手間はかかりますが、エアコンや温風ヒーターと比べ、体の芯まで届く遠赤外線を多く発するほか、薪のはぜる音を聞き、炎の揺らぎを目にしながら暖を取りますと身も心も幸せな気分になれるところが魅力です。




話は変わって前回に引き続き、親子間における金銭消費貸借契約に関するお話です。親が持っている老後の生活資金を子どもの住宅の取得資金として貸し付け、貸したお金は何年かに分割して子どもから返済してもらうことにより、子どもの住宅取得の助けとなる一方で、貸した方の親は、その返済金を老後の生活資金に充てることができるというスキーム(=枠組み)です。
このスキームを成功させるために有効なのが金銭消費貸借契約です。金銭消費貸借契約に記載する必要がある項目は、以下の通りです。
1.貸し借りする金額、2.返済方法、3.返済期日、4.利息
実際の記載例(利息を付けない場合)
第1条 貸主は借主に対して、令和7年5月1日金1000万円を貸し付け、借主はこれを借り受ける。
第2条 前条の貸し付けは、貸主が前条に定める金員を、借主が別途指定する銀行口座に振り込む方法により行う。なお、振込手数料は借主の負担とする。
第3条 借主は貸主に対して、第1条に定める貸付元本を、令和7年6月以降、毎月末に5万円ずつ貸主の指定する銀行口座に振り込んで返済するものとし、利息は付さないものとする。
本文は以上の通りですが、これに貸主及び借主の住所、氏名を記載し、印鑑を捺印します。印鑑は実印が良いでしょう。また、金銭消費貸借契約書にはその金額に応じて印紙を貼付し消印をする必要があります。貸し借りする金額が1000万円の場合は1契約書につき印紙は1万円です。
次回も、この金銭消費貸借契約に関して留意すべき点についてお話ししたいと思います。